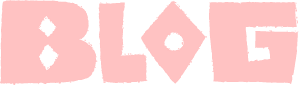2021.08.20 Fri
三題噺百景
三題噺百景〜序〜
2021年4月15日昼過ぎに、放送作家のMさんから久しぶりのメールが届いた。内容は「ニッポン放送『ラジオビバリー昼ズ』生放送内で三題噺をやってくれませんか?」というもの。5月の4週に渡って、若手落語家が生放送内でお題をもらって、2〜3分の噺に仕上げて発表するというタフな企画への出演オファーだ。
二つ返事で快諾するには厳しい条件が揃っている。ヤラセ無しで本当にその場でネタを作るとのことだから、下手をしたら何にも思いつかない可能性もある。そうなったら放送事故だ。さらには司会の春風亭昇太師匠の前で下手な高座を勤めるわけにはいかないからプレッシャーもあるし、そのわりに短時間のラジオ出演だから出演料は微々たるものだ(ギャラが50万円とかであればどれだけタフな企画でも二つ返事で出演するに決まっている)。
バスケットボールBリーグの優勝決定戦・横浜アリーナの真ん中でオーダーメイド落語をやったり、両国国技館で開催された音楽フェスのオープニングアクトとして1万人の前で高座を勤めたりと、信じられない仕事をこれまでこなしてきた僕は大抵の無茶な内容では驚かないし、むしろ楽しんで取り組める胆力を練ってきた。
それなのに、なぜそこまでラジオの生放送で三題噺を披露することに二の足を踏むのか。それは三題噺に対する苦手意識があったからだ。
これまで三題噺をやった経験は二度ある。どちらも柳家わさび兄さんとの二人会でのことだ。わさび兄さんは毎月の独演会で三題噺をライフワークのようにずっと取り組んでおられる若手三題噺プレイヤーの筆頭だ。そのわさび兄さんと、それこそ今回オファーを頂いた放送作家・Mさんが主催の『らくご@座』という企画で、三題噺の会をやって頂いた。
1回目は事前にお題を頂いて、1ヶ月くらいかけて噺を作ってくる形。2回目は柳家三三師匠をゲストにお招きして、その場でお題を決めて確か数十分くらいの短い時間で作り上げて披露するという形。
そのどちらもあまり手応えがなかった記憶がある。最初の方はお題にあった「星座」から、「いまは平面で構成される星座を、立体として構成しなおす」というような切り口のネタを作った。2回目の方は、どういうお題だったかすら忘れてしまったけど、苦し紛れに自分自身が登場するメタ的な話でお茶を濁したはずだ(落語家を登場させてメタ的に物語を作るのは、なんとなく逃げの技というか最終手段みたいな感じが三題噺の流儀としてある。そりゃ共感を生みやすいからネタは作りやすいに決まっているけど、そんな安易なところに逃げてどうする?みたいなことかと)。
一方で、例えば『吉笑ゼミ。』という自主イベントでは、哲学や物理などゲスト講師の講義を客席の後ろで聴き、10分の仲入りを挟んで講義内容を元に落語を一席披露する、という即興性の塊みたいな企画をやってきた。今や僕にとっての代表作と言えるくらいの『一人相撲』というネタも、実況アナウンサーである清野茂樹さんの講義を聴いて、その場で作ったネタだ。つまりは即興的な企画にはどちらかと言えば適正があるタイプのはずなのに、三題噺ではうまく力を発揮することができない。それがなぜか自分でも把握できていなかった。
とにかくビバリー昼ズで三題噺に挑戦すると決まってから、少しでもうまくいく確率を高めるために、というよりも大失敗する確率を減らすために練習を始めた。
「自分は誰よりも三題噺が下手」と仮定して、そこからうまくなるためにはまずは自分よりも上手な先輩方の実践例を調べて、自分との違いを明確にしていくべきだと思い、古今東西色々な三題噺の実践例を取り寄せて、連日稽古に取り組んだ。すると、すぐに「なぜ自分が三題噺が苦手なのか」という理由が判明した。
三題噺の基本的な見せ場は「一見無関係に思える3つのお題をいかにダイナミックに結びつけることができるか」というところにある。無造作に選ばれた3つの言葉が思いがけない結びつきをすることでカタルシスが生じる。その時のお題同士の結び付け方を楽しんでもらう、というのが基本線にある。
ところが自分の普段の創作スタイルは、興味を持った一つのお題を徹底的に掘り下げて、少しだけこれまでとは違う切り口を提示するというものだった(それをギミックと呼んでいる)。思い返せば「星座」のケースもそうだけど、与えられた3つのお題を普段の癖で掘り下げて、少し違う切り口を提示しようとする。ただ、そうやってギミックを生み出す作業は制作時間の限られた三題噺の仕組みとは相性が悪いのは明白だ。
さらに僕の作るネタはそうやって提示したいギミックを、論理的に行ったり来たりさせながら緻密にやり取りを組み込んで形にしていく。当然ながらそんな風に緻密に会話を組み上げることも時間制限がある三題噺では不可能に近い。
つまり、僕が普段得意にしている創作スキルが三題噺という仕組みではほとんど役に立たないのだ。そうやって少しだけ解像度を高めて三題噺を眺めることで、ようやく自分の現在地がわかったし、また今後どうするべきかということもわかった。
いま僕には三題噺の技術は初級・中級・上級の三段階あると認識できている。これは三題噺に対する解像度が上がったからに他ならない。それまでは漠然と「三題噺は難しい」としか思えていなかったものが、意識的に分解することで、三題噺の上手な先輩方がどういう技術を使われているのかが見えてきたのだ。逆に言えば今の僕の解像度ではまだ三段階にしか分けられないとも言える。とにかく三題噺の領域は少し踏み込んでいるととても奥が深い。
とにかく取り寄せた先輩方の実践例から、まずはお題だけを抜き出して、答えを見る前に自分も同じ時間で三題噺を作ってみる。その後で先輩の解答を見ることで、自分との発想や技術の差が浮かび上がってくるから、その繰り返しで少しずつ傾向と対策が見えてきた。
具体的なノウハウについてここで記すことはしないけど、そんな練習を繰り返していくうちに三題噺という競技ではとにかく三遊亭白鳥師匠が最高峰なのだとわかった(というか、自分の中でそう定義付けた)。
時間制限のある三題噺創作の中では僕が得意にしている「ギミック」や「緻密な構成」は機能しない。一方で大きな力になるのは「ストーリー展開」と「演者としての腕力」、そして最後の決め手は「サービス精神」だ。
同じ三題噺でも制作時間とネタ尺によってやるべき作業は変わってくる。例えばビバリー昼ズのように「1時間考えて3分のネタを作る」という制約であれば、求められるのは「なぞかけ力」と「サービス精神」だ。「2時間かけて25分ネタを作る」という制約であればもっと必要なのは「ストーリー展開」と「演者としての腕力」になってくる(ざっくり、前者で必要なのは先述した初級スキル、後者に必要なのは中級スキル)。
「ストーリー展開」は物語を前に進める力だ。お題のダイナミックな結びつきにカタルシスを感じる三題噺において有力な解法は、1つのお題を起点にストーリーを生み出し展開させていくことだ。ストーリー自体が展開している間は、お題が出てこなくても気にならない。そうやって、1つのお題を起点にとにかくストーリーを展開させて、展開させて、そしてその展開した先に気持ちよく次のお題が現れる瞬間を待つ。
思えば僕は普段の創作ではこのストーリー展開を意識的に排除してきた。物語展開で魅せるのでなく、むしろミニマルな、局地的な地点でごちゃごちゃと論理のみを展開して一本のネタに仕上げてしまう、そういう美学の上で創作してきた。これは大喜利的な方法論なのだとナツノカモという先輩に教えてもらった。「大喜利的な方法論」は物語をその場に引きとどめる力に他ならない。
考えてみたら大喜利的な方法論で物語をその場に引きとどめていても、次のお題にたどり着ける可能性は低い。そうじゃなくて、ストーリー展開によって物語をとにかく前に進めることで、気づけば次のお題に肉薄する地点までなんとかたどり着く、それが三題噺を成功させるための定石だったのだ。
ついでに書いておくと「演者としての腕力」はさらに強力なツールで、観客を退屈さえないためのストーリー展開すらうまく形にできなかった場合の最終手段として「とにかく演者としての自分の魅力」で観客を惹きつける。それは次のお題へたどり着くまでの場つなぎとして機能する。「サービス精神」もまぁ同じような理屈だ。
これを書いているいま、僕はビバリー昼ズで三題噺をやり、その5日後にも渋谷らくごで三題噺をやり、より精力的に取り組む意味を見出したことで、8月に『三題噺百景』という会を立ち上げ三日間連続で無事に三題噺を終えられた。
苦手だった数ヶ月前と比べて、明らかに技術は向上し、解像度も高まった。僕はいま中級の真ん中あたりを登っているんだろうなぁと認識している。
「なんで三題噺にハマったんですか?」と聞かれることが何度かあった。面白いネタ作るためと考えたら、わざわざ制限時間や三題の制約をつけずにフリーで創作した方がいいに決まっている。自分が関心あることや、伝えたいことを作品に昇華すればいい。それはこれから続けていく。
それなのに三題噺に向き合う理由は、まずライブ演芸としてものすごい力を秘めていると実感できたからだ。その場でもらったお題を起点に、まさにその場でネタが生まれるのだから、そのライブ感の高さは想像に易い。
そして何より自分がこれまで培ってきた技術が役に立たず新たな技を使わないと太刀打ちできにい競技だからこそ、やればやるほど全く違う自分に生まれ変われる気がするのだ。自分の知らない自分と出会うために、僕は三題噺百景を歩み始めた。これはそんな僕の脳内旅行記なのだ。