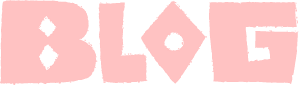2013.10.07 Mon
日常
森田真生さん
8月下旬だったと思う。
好きな漫画家さんが、ある週刊誌の連載コラムに挿絵を描いてらっしゃると知った。
タイミングが良かったのだろう、不思議なくらいフットワークが軽く、
すぐにコンビニへ週刊誌を買いに行くことができた。
目当ての週刊誌を手に取りペラペラとページをめくると、
すぐに見慣れた”見慣れないデザイン”の絵が視界に飛び込んできた。
抽象的なものでも、ポップでシンプルに、
しかも見たことの無いアイデアで絵に落とし込むことができる僕の好きな漫画家さんの、
いつも通りに好きな感じの絵だったので
「挿絵でもやっぱりチェックして良かったなぁ」
とホクホクした。
しばらくして何気なくコラムのタイトルを見ると『数学』の文字が含まれていて、
「おや?」
と思った。 ご存じのとおり?僕は数学が好きだ。
ページ下にあるプロフィール欄を見て
「おやおや?」
と思った。 著者の名前は見慣れないものだったけど、
すぐ隣に1985年生まれと書いてあったからだ。
1985年生まれ、つまり僕の一つ下だ。
同年代でこんな人がいるのかと驚き、家へ帰って著者のホームページにアクセスしてみた。
5年くらい前だったか、たぶん落語家になる前だったような気がするけど、
下北へ演劇を見に行った際にもらったチラシ群の中に
『数学の演奏会』というイベントのフライヤーが混ざっていた。
チラシでなくフライヤーと言いたくなるような洗練されたデザインもさることながら
「”数学”で、しかも”イベント”??なんじゃこりゃ?」
と驚いたのだけど、その時は結局イベントへ行かなかった。
しばらくして、そういったイベントがあるということさえ忘れていた。
そんな『数学の演奏会』というイベントを開催されているのが、
好きな漫画家さんが挿絵を担当されているコラムの著者である森田真生さんだったのだ。
「おやおやおや?」
近いうちに伺えそうなイベントはないかとスケジュール欄をチェックすると、
10月26日に池袋のコミュニティーカレッジでイベントをされると分かった。
「おやおやおやおや?」
コミュニティーカレッジと言えば僕も落語の講座を担当している西武のカルチャースクールだ。
ネット上に転がっている森田さんのインタビューなどを一通りチェックする。
「おやおやおやおやおや?」
少し前から京都に住まれているとのこと。
京都は僕の故郷だ。
このブログでも書いたし8月の勉強会などでも話したけど、
来年もしかしたら大学受験をするかもしれなくて、
そう思うに至ったいくつもある動機の中の1つに
「学問に携わっている人と知り合いたい」というものがあった矢先の出来事だったから、
なおさらテンションが上がってしまい、不躾ながらメールを送らせて頂くことにした。
一方的に思いを伝えるメールというは、
頂いたら嬉しいことには違いないけど、
何というか自分の心持ちとうまく一致したタイミングで受信できないと、
どう反応していいのか分からなかったり、でも返信しないというのも気がひけるし、
などとなんというかモヤモヤした感じになるものだと、経験則で知っていた。
落語家としてまだまだな状態の僕にもそういう類のメールを送って頂く機会が少しはある。
ありがた過ぎる話だ。
ましてや森田さんは普段から一方的に思いを伝えられることが少なくないだろうから、
よりタイミングが大事な気がするし、
というより、そもそもそういったメールで少しでも時間を奪ってしまうことが申し訳なく思えたりして、
どうしようかなぁ?どうしようかなぁ?とずいぶん迷ったりしたけど、
何しろ「おや?」がすでに5翻に達しており、
こちらとしてはとにかく一方的にでも気持ちを伝えないともうどうしようもない、
というくらいにまで思いが煮詰まってしまっているから、
いい歳して本気のラブレターを書いてしまった。
自分のことをまったく知らない方に、
何もない状態から自己紹介をして、気持ちを示して、という行為は、
思い返せば師匠に入門志願する時以来の体験だった。
///
そこから少しの時間が経ち、
気がつけば昨日、森田さんの前で落語を演ったり、これまでどういうネタを作ってきたかを話している自分がいた。
インタビューなどを読んで想定していた以上に、森田さんの思考は着実に深くまで進んでいて、
もちろん知識も豊富なので1つ1つのレスポンスが早くて、心底凄いなぁと思わされた。
同年代でこういう振る舞いをできる人に会ったのは初めてだった。
何より、笑いについての感覚がきちんと共有できることが嬉しかった。
夜が明けて、朝。
『粗粗茶』というネタの話をしていると、
「二重否定が肯定にならない場合」というエッセンスを抽出してくださり、
集合論的に見るのでなく、圏論的に見ると、これがこうなってこうなって、、とレクチャーして頂いた。
「そうそう、この感じを欲していたんだ僕は」
と嬉しくなったけど、圏論の考え方が難し過ぎて、
落語に活かせそうかどうかの前に、そもそも意味が分からなかったのだけど。。。
今回、佐渡に来て改めて思ったのは、
自分のテキストというか巻物というか振る舞いというか、
そういうものを持っている人に出会いたかったのだということで、
そして同じように僕も、
自分の言葉というか態度というか指針というか、
そういうものを持ちたいと思っている。